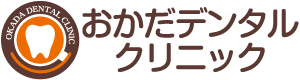歯ぐきのトラブル=歯周病について
歯周病とは、歯を支えている組織(歯ぐき・歯を支えている骨)に炎症や出血などが発生する感染症です。歯肉炎・歯周炎・歯槽膿漏などを総称して「歯周病」と呼びます。歯周病は、歯の表面に付着した歯垢(プラーク)の中の歯周病菌が原因で発症します。最初、歯と歯ぐきの間(歯周ポケット)に入り込んだ歯垢の中の歯周病菌が炎症を起こし、次第に膿みはじめ、最後には歯を支えることができなくなり歯が抜けてしまう、恐ろしい病です。
健康な歯肉
歯肉が健康なとき、歯は歯周組織によってしっかりと保持されています。
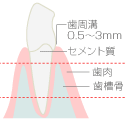

歯肉炎
歯の周りに歯垢(プラーク)がつくことで歯肉に炎症がおこり、歯ぐきが腫れるようになります。
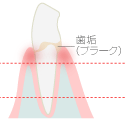

軽度歯周炎
歯周ポケットが深くなり、歯を支えている骨(歯槽骨)が溶けて喪失しだします。歯を磨くと出血も見られます。
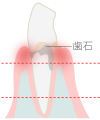

中等度歯周炎
歯槽骨の喪失が増え、歯が動くようになります。膿(うみ)がでることもあり、口臭も気になります。
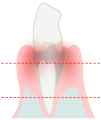

重度歯周炎
歯槽骨が2/3以上喪失し、歯がグラグラになり、やがては抜けてしまいます。口臭はよりきつくなります。
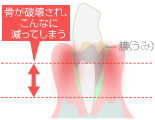
「もしかして歯周病?」と思ったらセルフチェック
初期の歯周病には自覚症状がほとんどありません。そのため、ほとんどの患者様はある程度進行してから歯科医院にかかることになります。ですが、溶けてしまった歯の骨は元には戻りません。手遅れになる前に、下記のセルフチェックを行い、気になる症状があれば歯科医院でのチェックをおすすめいたします。







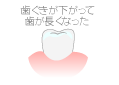

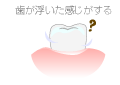
歯周病が身体にもたらす悪影響
歯周病になってしまうと、体のほかの部分にも悪影響を及ぼします。歯周病菌の毒素が血流に乗って体中を駆け巡ると、さまざまな臓器の機能を低下させてしまいます。糖尿病、早産(低体重児の出産)、脳卒中、心疾患、心筋梗塞、細菌性心内膜炎、肺炎などと歯周病との関連の報告例もあります。

歯周病の治療について
歯周ポケット掻爬術(新付着術)
比較的浅い歯周ポケットに対しては、歯周ポケット掻爬術(そうはじゅつ)で治療を進めます。
- 手術の前に麻酔を行います。
- 麻酔が効いてきたら、歯石を取り除きます。
- 炎症を起こしている組織をメスで取り除きます。
※前歯の治療などでは、術後に歯肉が露出するのを防ぐために、歯周ポケット内壁の歯肉をメスで切開してから歯石などを取り除きます。(新付着術) - 歯周ポケット内がきれいになったら傷口を縫合します。治療後は歯周ポケットのないきれいな歯肉に戻ります。
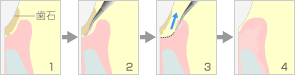
歯肉剥離掻爬術
基本治療を行っても歯周ポケットが残っている場合は、歯肉剥離掻爬術(しにくはくりそうは術)で治療を進めます。
- 手術の前に麻酔を行います。
- 麻酔が効いてきたら、歯肉を切開し剥します。
- 歯周ポケットの奥にある歯石や炎症を起こしている組織などを除去します。
- 歯肉を元に戻し、特殊なパックで傷口を覆います。
- 治療後は歯周ポケットのないきれいな歯肉に戻ります。
※歯肉が増殖している場合などは、増えてしまった歯肉を切除し(歯肉切除術)、歯周ポケットのないきれいな歯肉に戻します。
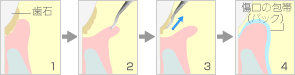
歯周組織再生療法
歯周病が進行すると、歯の周りの骨(歯槽骨)が喪失してしまいます。骨が溶けてしまうと歯肉の位置が下がって歯の根の部分が露出して歯がしみてきたり、歯が長くなったように見えたりします。歯周組織再生療法は、溶けてしまった骨を回復させ、歯肉の状態を健康な状態に戻し、歯の寿命を延ばす治療法です。
※ただし、歯槽骨の吸収が著しい症状では治癒が期待できないため、治療を行えない場合があります。
GTR法
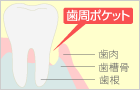
歯周外科手術で歯肉を取り除くと、骨の治る速度が歯肉が治る速度より遅いため、本来は硬い組織である骨を再生させたい場所に歯肉などのやわらかい組織が再生されてしまいます。それを防ぐために特殊な人工膜を一定期間埋め込み、骨が再生される空間を確保し、骨や線維組織などの歯周組織の再生を促します。
GTR法を行わない場合
先に歯の根と歯肉がくっついてしまうため、歯槽骨や歯根膜などがきちんと再生されません。
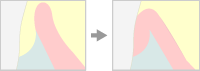
GTR法を用いた場合
- 歯根と歯肉の間に人工の膜を入れ、骨や線維組織が再生するための隙間をつくります。
- 歯周組織が再生したら、人工の膜を取り除きます。
- 骨、線維組織、歯肉が正しい状態に再生され、健康な状態に近い歯肉に戻ります。
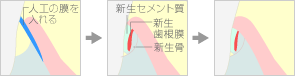
エムドゲイン法
歯周組織再生誘導剤であるエムドゲインゲルを使用し、歯周組織の再生を促します。エムドゲインゲルの主成分は、子供の頃、歯が生えてくるときに重要な働きをするといわれているたんぱく質の一種です。これを歯周外科手術の傷口に塗布することにより、歯が生える過程に似た環境を周囲に再現することで失われた歯肉や歯周組織を再生し、歯ぐきを元の状態に戻します。
- 麻酔をしたあと、治療をする部分の歯肉を切開し、歯石などの除去を行います(歯周外科治療)。
- 除去してできた空間に、エムドゲインゲルを塗布します。
- 傷口を縫合します。エムドゲインゲルが歯周組織の再生を促し、歯肉が正しい状態に再生され、健康な状態に近い歯肉に戻ります。
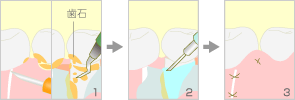
※歯周外科治療や歯周組織再生療法でも歯周病が改善せず、歯を失ってしまった場合にはインプラント(人工歯根を植える)治療などを行い失った歯を補う方法があります。